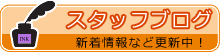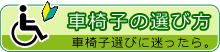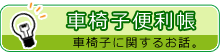母とリクライニング車椅子|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター
- ティルト・リクライニング車椅子
- 母とリクライニング車椅子
母とリクライニング車椅子

救急隊の車椅子

-
私の母は3年前から病気の後遺症で車椅子をつかっています。 ひとくちに車椅子といってもさまざまな種類があり、 形も大きさもいろいろと細かく違っています。
それは使う人の体の状態によって使い分けるためで、 私の母も、この数年でまざまな車椅子に乗ってきました。 車椅子を変えるたびに「こんなにもバリエーションがあるのか」といつも驚かされるのです。 母が最初に乗った車椅子は救急隊のものでした。 母が脳梗塞で倒れたのは小さな公民館の2階で、 そこはエレベーターがとても狭く、救急車を呼んだときに 「ストレッチャーが入るのかな」と皆で心配していました。
すると救急隊は車椅子型にもなるストレッチャーを使ったのです。 母は座った姿勢のままエレベーターを降りていき、 救急隊に乗り込む際はストレッチャーを倒して横になって運ばれていきました。
使用したのはリクライニング車椅子

-
手術の後、回復しましたが、脳梗塞の後遺症はかなり深刻でした。 立って歩くどころか上半身を起こすことすらできません。 入院先でリハビリを重ねてようやく「車椅子に乗る練習をしよう」 とお借りした車椅子は、リクライニング車椅子でした。
リクライニング車椅子は、その名のとおり座席をリクライニングすることができ、 横になるとまではいかないものの、かなりの角度をつけて楽な姿勢で座ることができます。 一般的な車椅子にくらべると大型ですし、 頭を支える枕のようなもの(ヘッドレスト)が突き出ています。
母はそんな大きな車椅子にようやく座らされているのでした。 半年ほどそんな状態がつづきましたが、 だんだんと回復してくると、やがてヘッドレストはいらなくなりました。 上体がしっかりしてきたため、頭をもたせかけなくても ある程度は自力で座ることができるようになったのです。
また、病院を退院し在宅介護になったため、 同じリクライニング車椅子でもかなり小さめの車椅子に乗り換えました。 家の中で動きやすいようにと考えたのです。
リクライニング車椅子の不便な点

-
在宅介護にうつってからももちろんリハビリは続けました。 その甲斐あって母はめきめきと元気になり、 精神的にも回復して再び人生を楽しみたいと思うようになりました。
買い物とか旅行とか、楽しみを探して外に出かけたいと言いだしたのです。 そこで障害になるのが車椅子でした。 当時使っていたのはリクライニング車椅子、 しかもタイヤの小さな介助式のものです。
はっきりいってこのタイプの車椅子はお出かけ向きとは言えません。 種類にもよるのですが、車輪が小さいためたった一段の段差さえ越えられず、 町歩きなどをすると非常に苦労が多いのです。 しかも重さは25㎏もありました。
なんとかもっと気楽に遊びに出かけられるようにならないものかと私は考えました。 そこで、もっとタイヤが大きくて段差にも強い、 標準タイプの車椅子を使うことにしました。
お出かけ用に標準型車椅子

-
標準型車椅子は段差には強いですが、背もたれがまっすぐです。 理学療法士さんには「上体が不安定だから、 まだ早いかもしれないよ」と言われていましたが、 いざ乗ってみると意外に大丈夫でした。
たしかに少し不安定で左へ傾きがちでしたが、 母はじきに慣れて、自分で「よいしょ、よいしょ」と姿勢を正すようになってきました。 そんなことができるんだねと、理学療法士さんは驚いていました。 標準型車椅子になって、母の活動の幅はぐんと広がりました。
ちょっとした段差であきらめていたカフェに入ったり、 孫をつれて遊園地に遊びにいったり、公園の池のまわりを散歩したり。 外へ出かける回数が増えるとともに表情が明るくなり、 話す言葉の数も増えて、母の人生はみごとに輝きを取り戻しました。
目標に向かってがんばる母

-
「この車椅子に乗れるようになってよかった」と、母は笑顔で車椅子をさすります。 介護用車椅子から標準型車椅子へ。その効果は本当に劇的でした。
そして次の目標もまた、車椅子です。 「今度は、自分で車椅子を動かしたい」と母は言います。 今は他人に押してもらうタイプのものを使っているのですが、 自走式といって自分で押して動かせる車椅子に乗りたいというのです。
「電動車いすにもちょっと憧れるねえ、あれカッコいいじゃない?」 母はわくわくしながら話します。
現在、母は自走式車椅子の練習を始めています。 筋力が弱いためなかなか難しそうですが、目標に向かって頑張っています。 母のような人たちにとって車椅子はただの移動手段ではありません。 車椅子は外の世界へ出ていくための大事な扉であり、 社会とつながるための橋であり、自由を手に入れるための光なのです。
この記事に関連したオススメ車椅子
-

- リクライニング・ティルティングなどが可能な車椅子。
リクライニングの車椅子