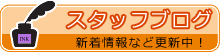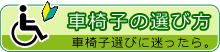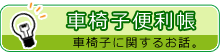電動車いすの危険性|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

電動車いすの危険性

楽になるということは

-
さて、電動車いすの便利性について述べましたが、 楽になるということは利用者にとっては大変有益でもあり毒となることもあります。
それは、利用者の機能低下をもたらす、活動レベルを制限する、心理的にも変化が現れます。
私たちは何か行動する時は自分の足で移動し、小さな活動は手を使って片づけをする、 取り出しをするなどしますが、電動車いすは足となり手ともなるのです。
キャスターのついたワゴンなど、電動車いすの足のせ台にリーチャーのような フックを着けることで 自由に動かすことができます。この時、電動車いすは手となっているのです。
利用者の立場に立って

-
利用者の立場に立ってどのように使うべきかを利用者と相談しながら、 利用可否、採用機種の決定、または医者の判断によって行うことが最も重要です。
電動車いすの安易な採用は、その後の利用者の人生を判断させ、 時には生活の混乱を招く危険性もあるため、 今後も電動車いすの更なる開発や普及が求められていくと考えられます。
電動車いすは手動操作のため自分の力で操作レバーを動かせるかどうかという判断基準があります。
メインスイッチを自力で操作できるか、手を操作レバーに固定しておくことができるかなどありますが、 顎操作での車いすもあるため障害の程度によってそのような車いすの使い分けが出てきます。
この記事に関連したオススメ車椅子
-

- 狭い室内でも使いやすい、コンパクトやスリムな車椅子一覧です。
室内用車椅子