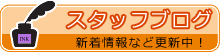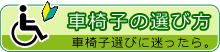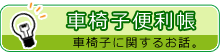車椅子の各部位は利用者の方や介助者の方をサポートするために大切な役割を持っています。
この記事では、車椅子の各部位の名称と機能について紹介します。
車椅子を正しく使用するため、使用前に各部位の役割を確認することをおすすめします。
車椅子の各部位の名称を紹介!介助者に確認して欲しい注意点も

- 車椅子卸センター
- 車椅子の各部位の名称を紹介!介助者に確認して欲しい注意点も
車椅子の名称って?
車椅子の部位別の名称と機能
車椅子の部位別の名称と機能
車椅子は利用者の方の生活をサポートするさまざまな機能が搭載されています。
車椅子を日々活用するためには、機能を知っておくと便利です。
車椅子の各部位の名称

車椅子の各部位の機能
1. バックサポート
車椅子の利用者が寄りかかるための背もたれです。
車椅子によってはリクライニング機能やバックサポートの張り具合を調整できるものがあります。
張り具合を調節することでより背中にフィットさせることができ、長時間座る場合のストレスを軽減することができます。
2. アームサポート
車椅子の利用者が腕を置くための肘掛けです。利用者が立ち上がる際の支えにもなります。
またアームサポートは車椅子の利用中の方が姿勢を保つために必要なため、安定性の高いアームサポートを選びましょう。
安定性の高いアームサポートとは自身の身体にあった高さのアームサポートを指します。
アームサポートの高さ調節機能がある機種(アームサポートモジュール)も存在します。
ベッドやトイレへの乗り移りが便利になるアームサポートを跳ね上げ、また着脱できる車椅子もあります。
3. サイドガード
車椅子使用中に、利用者の衣類が車輪に巻き込まれることを防ぐための部品です。
車椅子での移動中は衣類が車椅子の車輪に巻き込まれてしまうことがあります。
座面の両側にサイドガードを配置することで、巻き込みによる事故や衣服の破損を防ぎます。
4. シート
車椅子の座面で、利用者が腰かける場所です。座シートとも呼ばれます。
快適に使用するためには、身体のサイズに合った座幅が求められます。
5. レッグサポート
車椅子から、利用者の足が落ちないように足を支える脚部に掛かっているベルト部分の事です。
基本的にはシートと同じ素材の物が主ですが、下腿を支える部分がパッド上になっており、左右で独立しているタイプなどもあります。
6. フットサポート
車椅子の利用者が足を乗せる部分です。
基本的に折りたたむことができ、乗り降りの際は、フットサポートが邪魔にならないよう折りたたみます。
7. キャスター(前輪)
主に方向転換の際に使われます。後輪にくらべて直径が小さいことが特徴です。
8. 手押しハンドル
介助者が車椅子の移動や操作をするときに使用します。介助者が握り、方向転換などを行います。
9. 介助用ブレーキ
車椅子の手押しハンドルには介助者用のブレーキがついていることが一般的です。
下り坂では、車椅子のスピードを制御しながら進むことができます。
左右のハンドルのレバーを引くことで、車椅子の動きを制御できます。
10. 駐車用ブレーキ
車椅子を固定するブレーキです。車椅子から乗り降りをする際は、
駐車ブレーキをかけないと車椅子だけが後方へ滑り、利用者の方が転倒する恐れがあります。
駐車用ブレーキは車椅子を固定するため、乗り降りの際は必ずブレーキをかける必要があります。
車椅子の利用者が立ち上がると自動でブレーキがかかるタイプもあります。
11. ティッピングレバー
段差を乗り越えるときなどに介助者が使います。
介助者がティッピングレバーに足をかけて下に踏み込むと前輪を浮かすことができるため、乗り越えが容易になります。
12. 駆動輪(後輪)
駆動輪は自走型の車椅子や電動車椅子に駆動力を与える役割があります。
自走型の場合、利用者自らが駆動輪を回転させることで前進が可能です。
駆動力を大きくするため、大きく設計されている点が特徴です。
タイヤの種類は、主にエアタイヤとノーパンクタイヤの2種類です。
空気の補充が必要なエアタイヤはクッション性が高く、屋外で使用するのに適しています。
一方、ノーパンクタイヤは空気の補充が必要なく、空気抜けの心配もないのでお手入れが簡単です。
13. ハンドリム
後輪の外側についているリングのことを指します。自走式車椅子を利用者が手でこぐ際に使います。
両手でつかんで前方に押し出すことで、車椅子を前進させることが可能です。
車椅子を動かす前にすべきこと
車椅子を安全に動かすためには、いくつか事前にチェックしておかなければならないことがあります。
確認を怠ると、事故や利用者の方の怪我が起きかねません。車椅子を使っている場合は、日常的に以下のような確認を行いましょう。
●車椅子を点検する
安全利用するため動かす前に車椅子の各部位を必ず点検します。
特に重要なのがブレーキの動作です。各ブレーキが正常に作動するか確認しておく必要があります。
ブレーキの故障は万が一の事故にもつながるため、日常的に点検してください。
エアタイヤの場合、タイヤの空気圧を確認しておくことも大切です。
空気圧が低いと、地面の衝撃を吸収できないため、利用者の負担につながります。後輪が重く感じ操作性も悪くなります。
また、シートにたるみがあると利用者の姿勢悪化につながる可能性があります。
使用前にはたるみを確認してください。必要に応じて、クッションなどを置き、座り心地を調節してください。
経年劣化によって各部品の耐久性が落ちていることも考えられます。がたつきや破損にも注意が必要です。
●介助者は自身の服装を確認する
介助者が車椅子を動かすために支障がない服装かあらかじめ確認しておきましょう。
具体的には、動きやすい服装か、アクセサリーはついてないか、といった点を確認してください。
特にアクセサリーについては指や腕についたものは邪魔になるほか、
利用者の方に当たり怪我をさせる恐れがあるため、身に付けないことが理想です。
車椅子の移動中に介助者が注意すべきこと
車椅子での移動中、介助者は以下のような点に気をつけなければなりません。ここでは、注意すべきことを解説します。
●手や足が正しい位置にあるか確認する
車椅子の利用者の手や足が後輪などに当たらないよう正しい位置にあるか確認してください。
特に車輪への巻き込みは大きな怪我につながります。移動中に手や足の位置がずれやすいので意識的に確認するようにしてください。
●長時間座らせ過ぎないようにする
車椅子の製品によっては、長い時間車椅子に座っていると、利用者が痛みを感じることもあります。
長時間無理な座り方を続けていると、身体に悪影響が出かねません。
そのため、利用者の方を車椅子に座らせ過ぎないようにすることも大切です。
車椅子上で過ごす時間の長い方はリクライニングやティルティング機能付き車椅子をご検討ください。
背もたれの角度を変更することにより、座圧を軽減することができます。
●慎重に移動する
車椅子の使用中は、慎重に移動するように心がけてください。
急な方向転換やスピードアップは、利用者の方に不安を与えかねません。
適切なスピードかどうか、たびたび利用者の方に確認してください。
不注意で、周囲の人にぶつかってしまうこともあるため、周囲の状況に気を配りましょう。
坂道や段差では特に注意が必要です。
下り坂では、安全のため介助者が進行方向に対して背を向け、後ろ向きにゆっくりと下がっていくことが推奨されています。
車椅子は重量があるため、利用中は基本的に持ち上げないでください。
本体フレーム以外を持つと破損につながります。
段差を乗り越える際は必ずティッピングレバーを使用して角度をつけ、無理なく段差を乗り越えるようにしてください。
車椅子の利用は各部位の役割を確認し安全に操作することが大切です
車椅子は足が不自由な方が自身で動けるように、また介助者が操作しやすいように設計されています。
各部位は利用者や介助のための工夫が凝らされているため、使用する前に使い方を確認しておくことが大切です。
使用中は服が巻き込まれているなどの異常がないか確認しながら移動してください。今回紹介しているポイントを意識し、安全に車椅子を利用してください。