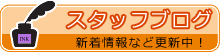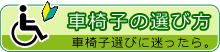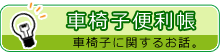自走式車椅子についての話|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター
- 自走式車椅子についての話
自走式車椅子についての話

自走式車椅子についての話

-
自走式車椅子は、自走式もしくは自操式といいます。
大車輪の外側にあるハンドリムという
金属製の輪を前方もしくは後方に回すことにより、 車椅子を前進後進することができます。
これは車椅子利用者が自身で動かします。
後輪のサイズは20インチ~25インチ程度とされています。
ただし、動作性の問題から大径のものを選択する利用者も多いようです。
車椅子の構造

-
駆動部はハンドリムとブレーキで構成されています。
ハンドリムには標準型とノブ付、片手駆動用があり、それらは障害の程度によって分けられます。
グリップはハンドルともいい、介助者が押して使用する際の駆動部で、 自走時は後方に転倒した時の頭部を保護する役割があります。
車輪は大車輪と小車輪があり、大車輪は車いす走行時の中心部分で、 リム、スポーク、ハブなどの部品でできています。
小車輪のキャスターは、タイヤ、リム、スポーク、アクスル、ヨーク、ナット、ステム、 フロントパイプという部品からなっており、 そのキャスターの車軸は走行時約30度後方に位置するように作られています。
タイヤの種類

-
また、キャスターは全方向に回旋することができ、 役割としては、段差がある際にその障害を乗り越えるために役立ちます。
しかし、全長全幅が長くなると、走行回転時には広いスペースが必要となることがあります。
後輪タイヤには、ソリッドタイヤ、エアタイヤ、チューブレス空気入りタイヤなどがあります。
ソリッドタイヤはゴム製で固くやや細いですが、長所はタイヤのパンクの心配がないこと、 平地ではスピードを出しやすく推進しやすいことがあげられます。
チューブレス空気入りタイヤは、チューブとタイヤが一体型で空気が直接タイヤに入っており、 スポーツ用あるいはレース用の車椅子として使われます。
フレーム部

-
フレームは金属製のパイプで、たすき、ティッピングレバー、転倒防止装置とがあります。
たすきとは車椅子のフレームの左右をたすきがけに連結してあり、 見た目がX型、2本のバーで中央部には軸心があります。
折り畳み式車椅子では必須の部分です。このバーの動きによって折り畳みと開きが自由に行えます。
前方のバーをクロスパイプ、後方のバーをクロスバーというため、別名クロスロッドともいいます。 ティッピングレバーはベースパイプが後方に延長されたレバーのことでこれは自走用ではなく、 介助者が車椅子を操作する際にキャスターを上げる時に使用するものです。
転倒防止装置

-
転倒防止装置ですが、前方転倒防止装置と後方転倒防止装置とがあり、 前方転倒防止装置はレッグパイプに取り付けられた棒状の装置のことであり、 後方転倒防止装置はティッビングレバーの先端を床面に曲げて 着地させて安定させている棒状もしくはキャスター付きの装置です。
適応とするのは脊髄損傷患者の車椅子から床へのトランスファー、もしくはキャスター上げです。 付属品としてシートクッション、シートボードなどがあります。
シートクッションは厚さ10cm前後のクッションでウレタンフォームやラバー製が多いようです。
シートボードはシートクッションより固く中央部がカットされています。