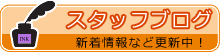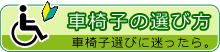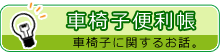車椅子への移乗|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】
yyyyyyyyyyy
- 車椅子卸センター
- 車椅子への移乗
車椅子への移乗

車椅子への移乗

-
車椅子への移乗はその場に合ったいろいろな移乗方法があります。
・スライディングボードを使用する 主として、ベッドと車椅子間の移乗 ベッドからストレッチャー間の移乗に使われます。 スライディングボードで座面が動くタイプもあります。
また、スライディングボードを使用する際は、 車椅子のアームレスト(肘掛)を外せるタイプ、 又は、跳ね上げるタイプを使用すると、移乗しやすくなります。
移乗させることが多い場合、車椅子を選ぶポイントとなるでしょう。 ・介助用ベルトを使用する ・回転盤を使用するなど いろいろな車椅子の移乗グッズも存在します。
道具を使わない方法では

-
道具を使わない方法
①介護の方が片足を相手の膝のあいだに差し込んで、 腰を支えながら立ち上がらせます。
②介護の方の膝で相手の膝を支えながら、車いすの方へお尻を向けます。
③ゆっくりと腰を下ろしてもらいます。
※「いち、にのさん」と声をかけながら、おたがいに協力しあうことが大切です。
注意!車椅子に座る前にままず駐車ブレーキが
かかっていることを確認しましょう。
移乗時の注意点

-
介助式車いすに乗せる際は、車いす利用者の各々の状況や障害によって異なる注意点があります。
どのような状況なのか、障害はどの程度なのか、 また車いす利用者が自力で動けるようならなるべく動かしてあげるようにするなど、 介助者は瞬時に判断し行動しなければなりません。
これは介助者にとってとても大切な使命であり義務でもあります。 介助者は車いす利用者の体に責任を持ちますから、そのことをよく念頭に置いて準備しましょう。
介助者も体の準備を

-
介助者は介助する際、腰にかなりの負担がかかります。
腰痛防止のためしっかりとストレッチを行いましょう。 そして、実際に車いすに移乗する際車いすが動かないようにブレーキを必ずかけロックしておきます。
フットレストは上げておきます。 半身麻痺の方には症状改善のため、なるべく自力で移動するようにサポートするのみに徹しましょう。
介助の際の大事なこと

-
車椅子を選ぶ際には移乗がスムーズに行えるように、 車いすの種類としてフットレストが簡単に取り外せたり アームレストがはねあがったりするタイプのものもあります。
そういったものを考慮した上で車いすを選ぶと良いでしょう。 そして、介助者にとって、なにより大事なことは車いす利用者からの安心感と信頼感を得ることです。
介助者の姿勢が正しく安定することはもちろん、 常にコミュニケーションをとることで、車いす利用者から「この人は信頼のおける人だ」 「この人にだったら自分の体をゆだねても大丈夫だ」と思ってもらえるようにしましょう。
介助式車いすへの移乗

-
半身麻痺をお持ちの方は、麻痺がない側のベッドに対して 約30度くらいの向きに車いすを置きます。
そして、介助者の補助を借りながら自分でアームレストにつかまり 筋肉をなるべく使うようにして車いすに移乗します。
この時、体を動かすたびに重心が移動しふらふらとしてしまう危険性があるため 車いすに乗る時は胴を支えて深く腰掛けさせ、 乗せた後も体のバランスがくずれないようしっかりと麻痺側を補助します。
移乗が全介助の場合

-
下半身不随の方の場合には、全介助となりますので二人での介助で行います。
車いす利用者の方に腕を組んでもらい、一人は後方に回って脇の下から腕をくぐらせ組んだ腕をつかみます。
もう一人は、車いす利用者の前方に立ち両ひざをかかえ安定した形で移乗させてあげます。
車いすに移乗した後は麻痺側から片方ずつ関節をゆっくりと動かしフットレストの上に乗せてあげましょう。
この時一瞬の気の緩みが事故につながりますので、緊張感を持ちながらも声掛けを忘れず移乗させてあげてください。
声かけで安心感を

-
車いすに乗った際の確認と言葉がけは大切です。
車いす利用者を車いすに乗せた際は「深く座れましたか?」「苦しい箇所はないですか?」 など声掛けを行い、「では前に進みます」との言葉で初めて車いすをゆっくりと動かします。
これから何をするか、後ろに進むのか、段差はあるのか、 エレベーターに乗せるのかなど常々気を付けながら言葉がけを行います。
乗った際の確認のポイントと声掛けとしては、 必ず前に回り、顔を見てから「痛いところはありますか?」 「どこかしっくりこないところはありませんか?」などと声をかけます。
この時は笑顔で安心感を与えてあげて下さい。もし何かあれば原因を調べて解決しましょう。
動く前のポイントは、これから何をするのかをお知らせしてからブレーキバーを介助します。
グリップを持ちまた言葉をかけてからゆっくりと発進します。
そしてまた話しかけながら進むことによって相手にリラックスさせます。
そうすることで、車いす利用者に不安感を取り除くこととリラックスをさせることが目的です。
移動できるという喜びを車いす利用者とともに分かち合いましょう。
この記事に関連したオススメ車椅子
-

- アームサポートを持ち上げると駆動輪が後方へ移動する移乗の事を考え開発された車椅子。
【MiKi/ミキ】横乗り ラクーネ2 LK-2