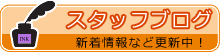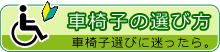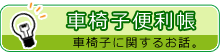車椅子とメンテナンス|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター
- 車椅子とメンテナンス
車椅子とメンテナンス

車椅子の保守と管理について

-
ここ数年で高齢者化が進み、若者がだんだんと少なくなっている。
最近では、高齢者も運転をするようになり、お店へ突っ込む事故なども多発している。 だからといって高齢者は免許を返納すべきかと言えば、必ずしもそうとは言えない。
高齢者は足腰が弱っており、車がなければ近くに買い物に行くのにも苦労する高齢者も少なくない。 そんなとき、活躍するのが「電動車椅子」である。
電動車椅子は通常の車椅子と違い、充電をすれば自動で走るという点が大きく違う。
例えば、通常の車椅子は介助者がいなければ少しの距離を進むにも相当しんどいが、 電動車椅子を使えばレバーを操作するだけで自動で進むので、介助者を必ずしも必要としない。
道路交通法でも電動車椅子は歩行者と同じ扱いとなっており、歩道を走ることが認められている。 そのため、足腰が不自由な高齢者層に、大きく普及している。
移動速度も3~8km程度と非常にゆっくりに制限されており、一見安全なように見える。
車椅子の保管

-
ところが、実際は事故が非常に多い。 電動車椅子は、通常の車椅子と違って動力が電気であるため、どんな段差や凹凸があっても構わず進む。
そのせいで、転倒事故が非常に多い。 些細な段差で車椅子が転倒したり、溝に倒れてしまったりと、自分で歩くよりも危険な事故が多い。
また、道交法では車道を走ることが認められていないにもかかわらず、実際には車道を走ってしまうお年寄りは非常に多い。
そのため、車やバイク、自転車との衝突事故が多発しているのである。
では、どうやってこうした事故を防げばいいのか。
こうした現状を知ってか知らずか、最近は運転免許証を返納した高齢者に対して、バスなどの公共交通機関の優遇をする自治体が増えてきている。
それにより、車がなくなっても公共交通機関を利用することで、不便を解消できるというのである。
しかし、実際には田舎などはそうした公共交通網が整備されているとは必ずしも言えない。
点検と手入れについて

-
そうした田舎では、巡回バスや乗り合いタクシーなどがある。
電動車椅子は自分で運転(操作)するため、自身の操作ミスで事故が起こるが、 バスやタクシーであれば、運転手が別にいるので、そうした操作ミスによる事故を防ぐことができる。
また、巡回バスなどのいいところは、お年寄りが定期的に乗っていることがわかれば、 ある日乗っていない時に自宅に確認したり、知り合いに確認することで、孤独死などを防ぐという役割もある。
こうしたいわゆる生存確認も、社会として大切な役割である。
また、電動車椅子にはもう一つの落とし穴がある。
近年、バリアフリー化が進み、障害となるものがかなり減ってきた。
しかし、電動車椅子のように自分自身の身体を鍛えないような行為を続けていると、 かえって体力の低下が進んだり、痴呆症が悪化するなどの見落としがちな副作用が現れる。
電動車椅子

-
そうしたことについて、最近ではバリアフリーではなく、あえてバリアを作ることが良いということが少しずつわかってきている。
最初から障害をなくしていると、高齢者自身が判断することが少なくなり、痴呆が悪化するということがわかってきている。
障害がない環境に慣れてしまうと、障害がある環境に入った時、それを避けようとする傾向があるということもわかっている。
しかし、逆にバリアをそのままにしておくと、自分自身でどうやってそれを乗り越えるかという判断能力が培われ、痴呆が改善されるということが報告されている。
つまり、電動車椅子を使うよりも、かえって自分自身で歩いて行けるところに自分の体力・判断で行くということのほうが大切なのである。
介助者の方もつい手伝ったりしてしまうものだが、本人ができるものは本人にさせるということが何よりも大切である。
このことから感じるのは、私たちはつい便利なもの、楽なものを選びがちになるが、障害があり不便なものを選んだほうが、かえって良い結果を生むということだ。 このことは、高齢者でなくても身に染みて覚えておくべきだろう。