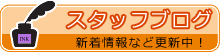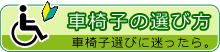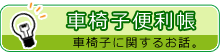車椅子が故障したとき2|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター
- 車椅子が故障したとき2
車椅子が故障したとき2

自分たちで修理

-
しかし介護保険レンタル制度とは違い、 いつでも買える、すぐに修理できる、というものではありません。 市町村に申請し、判定を受けなければなりません。 かなり時間がかかることもあります。
耐久年数というものも定められています。 普通の車椅子でも電動車椅子でも6年です。 6年以内に新しいものに買いなおす場合はさらなる申請が必要となり、 そう簡単ではありません。
申請は大変面倒ですし、税金の無駄遣いもいけないことなので、 現実的には、少々の故障や不具合なら 自分たちで修理していかなくてはなりません。
家族による応急処置

-
これは障害者の家族や入所した施設の職員が行うことになります。 たとえばグリップが古くなってしまった場合は、 自転車用のグリップに付け替えることができます。
肘置きがはずれてしまった場合は、ウレタンやスポンジを切って肘置きを作り、 テープでぐるぐる巻きに貼りつけたりします。
背もたれが摩耗してきた場合は毛布やクッションをあてがい、固定します。 足が落ちないように支えるレッグベルトが傷んでしまった場合も 同様に自分たちで工夫して作りつけます。
素人の工作ですので見栄えはしませんが、 「足」が使えないことにはどうにもなりません。 修理できるとしても申請と判定を待たなくてはならず、 すぐというわけにはいかないので、多くの家庭や施設で このような応急処置が行われています。
新しい車椅子

-
制度では「6年」と定められていますが、 何年もつかはその人の身体状態や生活に大きく左右されます。 比較的元気で意欲があり、外へ出ることの多い人の車椅子は、 6年よりもずっと早く悪くなってしまうものです。 また、体の状態が悪化して、標準型の車椅子に座っていられなくなる場合もあります。 車椅子の形状は体圧分散にもかかわってきますので、 褥瘡になると違う形のものに買い換える必要もでてきます。
修理のための申請や判定に長い時間がかかって車椅子が使えない状態が続くことは、 障害をもつ人たちにとっては大変な負担になります。 「足」が使えないということは車が壊れたり靴が傷んだりするよりも困ることです。 障がい者と介護者は、壊れた「足」を自分たちで工夫しながらなんとか繕いながら 長い手続きが終わり新しい車椅子を手に入れられる日を待っているのです。
この記事に関連したオススメ車椅子
-

- ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル。
【MiKi/ミキ】BALシリーズ BAL-2【完売しました。】