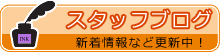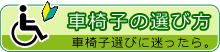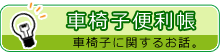車いすの利用とその注意点|車いすにまつわる話【格安通販の車椅子卸センター】

- 車椅子卸センター
- 車いすの利用とその注意点
車いすの利用とその注意点

車いすの種類

-
車いすは、いすの部分と車輪の部分から構成され、 高齢者や下肢や体幹などに障害がある人の移動を補助する道具です。 車いすを利用することで利用者の日常生活の行動範囲を広がります。 また、自分で好きなところに移動できるようになるため、 自立心が養われるといったメリットがあります。 車いすの種類には、自走用車いす、電動車いすそして介助用車いすがあります。
自走用車いすはブレーキが後輪の前側にあり、 手動で動くため利用者自身が操作して移動することができます。 また、座席の下に備え付けられたバッテリーを使って 車輪を電動モーターで動かす電動車いすは、 自走は困難だけれども電動ならば操作ができるといった人や、 自走もできるけれども電動車いすと組み合わせて移動を 行いたいという人によく利用されています。
どのような目的で車いすを使うのか

-
自走式車いすも電動式車いすもどちらも利用者本人が 操作することを前提とした車いすであるといえます。 それに対し、介助者が移動操作を行うこと前提にした車いすもあります。 このような車いすは介助用車いすとよばれます。 介助用車いすは自走用車いすに比べると後輪の直径が小さく、 操作しやすいのが特徴です。ブレーキは介助者が使用するため、 後輪の後方についています。これらの車いすを活用することで 車いすの利用者はより効率的に移動できるようになるため、活動の幅が広がります。
車いすを選ぶ際には、どのような目的で車いすを使うのかを明確にしておく必要があります。 そのためには利用者の状態がどのようになっていて、 どのような介助が必要なのか、利用者本人や家族が どのような生活をしたいのかといった点について考え、 本人の状態やライフスタイルに合った車いすを選ぶようにします。
座り心地をよくする工夫

-
車いすに長時間座って移動する場合などは、 乗っていても疲れにくいといった乗り心地のよさを ある程度重視して選ぶといいといえます。
例えばクッションなどと組み合わせて座り心地を よくする工夫もできますので、利用者の意見だけでなく 介護者の視点も尊重して決めることが大切といえます。
実際に車いすを利用する場合には、 利用者が車いすに乗り換えることが必要になります。
利用者の安全性の観点から、介助者は 利用者の乗降時に次の点を注意しておかなければなりません。
介助者は確認を大切に。

-
一つ目は、ブレーキがきちんとかかっているかを確認しておくということです。
ブレーキがきちんとかかっていなければ、移乗の際に車いすが動いてしまったり、 利用者がふらついて倒れ込んでしまったりといった思わぬ事故につながります。 そのため、危険を未然に防ぐという意味でも、介助者は車いすに ブレーキがきちんとかかっているかを確認しておきます。
二つ目は、車いすの利用者が車いすから乗降する時には、 利用者の足がフットサポートに乗っていないことを確認しておくことが大切です。 フットサポートに足が乗ったまま利用者が車いすから降りると、 立ち上がろうとした時に車いすごと前に倒れてしまい、たいへん危険です。 そのため、必ずフットサポートを上に持ち上げ、 足をしっかりと地面につけた状態で車いすから降りるよう、サポートを行う必要があります。
利用者の自立心が養われることに期待できる車椅子

-
したがって、利用者が車いすに乗る時と降りる時には、 安全性の観点から介助者が車いすのブレーキがきちんとかかっており、 フットサポートが持ち上がった状態になっていることを しっかりと確認しておくことが重要といえます。 このように、車いすを利用することで利用者の日常生活の行動範囲が広がります。
また、自主的に移動できるようになるため、 利用者の自立心が養われるといったメリットがあります。 そして、介助者は安全性の観点から車いすの利用者の乗降の際には、 ブレーキがきちんとかかっており、 フットサポートが持ち上がった状態になっていることを確認することが大切です。
この記事に関連したオススメ車椅子
-

- 利用者が自分で漕いで移動できる車椅子
自走介助兼用の車椅子